豆についてはこんな感じになっています(種類がとても多い)
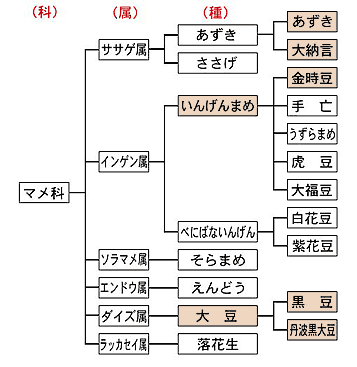
豆は、糖質とたんぱく質を供給し、脂質の取りすぎを抑えます。
豆は、ビタミンB1やKなどのビタミンを豊富に含んでいます。
豆は、現代人に不足しがちなミネラル、特にカルシウム、鉄、カリウム、亜鉛をたくさん供給します。
豆は、食物繊維の王様です。
1.脂質(脂肪)の過剰摂取を防ぎます
脂質はエネルギー源として必要ですが、多く取りすぎますと、心疾患、動脈硬化や糖尿病などを引き起こす大きな原因ともなってきます。日本も昔は日本型食生活によって上手に栄養バランスを保ってきたのですが、現代、特にここ最近では脂肪エネルギー比率(総摂取エネルギーの中で、脂質から摂取する割合)が健全なラインである25%を超え、さらに増加の傾向にあります。糖質は「日本人の栄養所要量」の中で「糖質の摂取量は総エネルギー比の少なくとも50%以上であることが望ましい」とされています。50%を切ってはいませんが、米の消費が減少したことによって57%台まで低下を続けています。
さて、豆のエネルギー構成をみますと、100g中、おおむねP(たんぱく質)20g、F(脂質)2g、C(糖質)54gと、一粒の中で極めてバランスの取れたエネルギー構成になっているのに驚かされます。
2.不足するビタミンを補います
ビタミンは、所要量は微量ですがいろいろな栄養素の働きを助けからだの調子を整える大事な役割をしています。ビタミンB1は糖質をエネルギーに変える手助けをしますが、不足するとエネルギーの生成がスムーズにいかず、尿酸などの疲労物質がたまって疲れやすくなります。また、脳や神経にエネルギーが十分に補給されないことから、イライラするようになります。現代の若い人たちは、清涼飲料水などを多く飲みがちですので、ことさらビタミンB1が不足しがちです。
豆は100gの中に0.5mg前後と多くのビタミンB1を含んでいるので、豆を毎日食べるだけでかなり補給できます。また、豆はB2やナイアシン(ニコチン酸)、E、K,などのビタミン含んでおり、いわば総合食品です。
3.不足しがちなミネラル(無機質)を豊富に供給します。
ミネラルは、体の機能の維持や調節に欠かせない栄養素です。体に必要なミネラルはたくさんの種類がありますが、所要量はそれぞれ微量です。しかし、不足すると、いろんな症状が現れます。
ミネラル はたらき 不足によって起こる症状
カルシウム リンと並んで健康な骨や歯を作ります。体の中には成人では1kg以上のカルシウムがあり、ミネラルの中では飛び抜けて多い含有量です。 骨や歯が弱り骨粗しょう症にもなりやすい。
イライラなど精神の不安定を招いたり血行に異常をきたします。
鉄 血液中の酸素を運搬します。 体の中に酸素が十分に供給されず、めまいや貧血、思考能力の低下 特に女性はライフステージを通して不足しがちです。
カリウム ナトリウムの排泄を促して血圧を下げます 日本人には食塩のとり過ぎの傾向があるため、積極的にカリウムを摂取する必要があります。
亜鉛 亜鉛は、たんぱく質の合成などの細胞の新生に不可欠です。 発育不全や身体の成長が妨げられたり肌ががさついたり、脱毛や爪の発育障害。
豆には、カルシウム、鉄、カリウム、亜鉛のいずれもが豊富に含まれています。
4. 食物繊維不足には『豆』がお応えします。
生活習慣病予防の為にも、食物繊維を十分にとる必要があります。食物繊維は成人で1日20g〜25gが必要とされています。
これまで一般に、食物繊維は体内で利用できず、単なる整腸作用のみ注目されていました。しかしながら、近年食物繊維の有する種々の機能性が明らかになりました。
具体的には、食物繊維には抗便秘作用や血清コレステロール値及び血糖値の改善効果が認められ、心疾患、動脈硬化症、糖尿病、腸疾患、特に大腸がんの予防に効果のあることが明らかにされています。
日本人が豆をたくさん食べていた頃には、食物繊維不足はありませんでしたが、今は食物繊維の飲料まで売られる時代です。豆には食物繊維が100g中17〜19gは入っており、食品の中でもトップクラスの含有量です。
中国医学も太鼓判!『豆』の効用
5000年の歴史を持つ豆のキキメ
中国医学は「医食同源」の考え方の上に成り立っており、その礎を築いたのが約5000年前の神話上の人物である神農皇帝(炎帝神農)です。皇帝は農業を振興させると同時に野山をかけめぐり、ありとあらゆるものを口にして自ら薬効と毒性を確かめ、365種類の医薬を発見したといわれます。
これらは、中国古書「神農本草経」では「上薬(じょうほん上品)」「中薬(ちゅうほん中品)」「下薬(げほん下品)」の3つのグループに分けられ、この中にだいず大豆おうかん黄巻や赤小豆が含まれています。
黒大豆で作られたもやしを乾かした大豆黄巻は、血行を良くし筋肉のけいれん痙攣や膝の痛み、しびれをとり、また、赤小豆は余分な水をとり腫れやできものを治すと記されています。
また、黒大豆は色素のアントシアンが鉄分と供給するため、鉄鍋で煮ると黒色がより美しくなります。